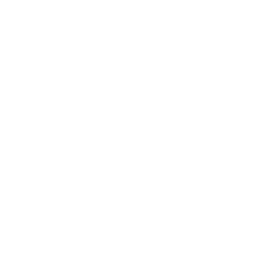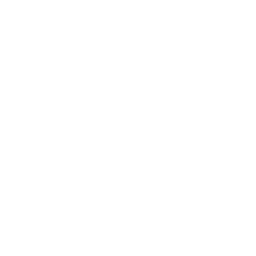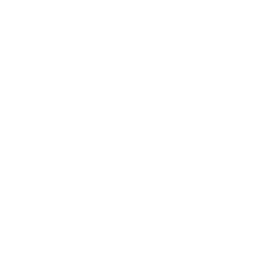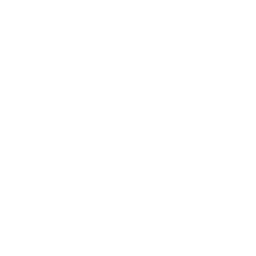子どもの歯磨きいつから?と上手に習慣づけるコツ
はじめまして!歯科衛生士のならはしです!この記事は、赤ちゃんを持つお母さんお父さん、特に初めての子育てで歯磨き習慣をどう始めればよいか悩む方に向けて作成しました。

子どもの歯磨きは「いつから始めるべきか」という基本から始まり、初期の道具選び、楽しく続けるコツ、親子での時間づくり、子どもの自立を促す工夫、適切なほめ方やごほうびの活用まで、実践的なポイントを網羅しています。
この記事を読むと、家庭での歯磨き習慣を無理なく取り入れて続ける方法が分かり、むし歯予防につながる日常の習慣づくりが具体的にイメージできます。
初めての育児で不安が多くても取り入れやすいコツを、分かりやすい言葉と段階的なアプローチで解説します。
まずは、子どもの歯磨き習慣をどの時点から意識し、どのように基本を作っていくかを、初めて子どもを迎えたご家族にも分かりやすく解説します。歯磨き習慣は早く始めるほど定着がよく、虫歯予防の土台をつくります。乳歯の生え始めからのケアが、将来的なお口の健康につながることをお話します。
いつから始めるべきかの目安
歯磨きの「始め時」は、歯が生え始めた瞬間ではなく、その前から考えていくと良いです。生後2~3か月のうちに、清潔なガーゼや布で歯ぐきを拭いたりします。お口の周りを触ったり保護者がきれいな手でお口の中や舌を触って慣れさせることができます。
次に「初めて歯が生えた頃」の時点で、歯が出ているのを発見したら、歯ブラシを使ってみましょう。。実際の生え始め時期は個人差がありますが、一般的には下記の時期感覚を目安にすると良いでしょう。
・0~6か月:歯が生え始める前。市販の歯磨きガーゼなどで歯ぐきと唇周りを清潔に拭いてみましょう。母乳やミルクの後に実行すると習慣化しやすいかもしれません

・6~10か月:初めて歯が生える時期。上の前歯2本、下の前歯が中心に出てきます。ここで、歯ブラシを検討。柔らかい毛先の子ども用歯ブラシを用意してみます。
歯磨き粉は使わなくても良いですし、使うのであれば子供用のものをごく少量(米粒程度)からスタートします。
・10~18か月:乳歯の生え揃いに向かい、歯みがきの習慣化を意識します。まだ親が主導で、歯ブラシに慣れる期間として、保護者が優しく補助します。
この時期のポイントは「回数よりも継続」です。無理に完璧を求めず、1日の中で歯みがきを1回でも良いので習慣化してみましょう。子どもの興味を引く工夫(音、リズム、遊びの要素)を取り入れつつ、リズム化していくと長続きします。
初期の歯みがき道具の選び方
初期の歯みがき道具は、成長段階に合わせて選ぶことが大切です。以下のポイントを押さえましょう。
1) 歯ブラシの選択基準 ・年齢に合わせた小さめサイズのヘッド 、柔らかい毛先、グリップが握りやすい太さと形状 ・安全性の高い設計(のどに突き刺さらないストッパーがついているなど)
2) 歯磨き粉の選び方 ・1歳頃までは基本的に歯磨き粉を使わなくても良いです。歯が生えそろう2歳半から3歳ころまでに徐々に慣れさせるように歯磨きジェルや子供用歯磨き粉を使うと良いでしょう。
年齢が進むにつれて、 フッ素を含む子ども用の歯磨き粉を選んでみてください。歯科医院で販売しているようなフッ素濃度がきちんと書いてあるものが安心です。
年齢によって使えるフッ素濃度が決まっているので歯科医院で先生か歯科衛生士に尋ねましょう。子供が好きな味を選べるように数種類あると楽しみが増えるでしょう。

3) 道具の使い方のコツ ・歯ブラシはお子さんの手が自分で持てるように、グリップを選び練習してみましょう。
昔は「ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境界に45度の角度で当て、優しく動かす」が多く言われてきましたが、これも良いですが子供には難しいので、ブラシが歯に当たること・優しく磨くことをまずは教えると良いと思います。
最終的には汚れが取れていることが目的なのでそれを保護者が意識しましょう。仕上げ磨きは、理想は小学校卒業までできると良いです。
4) 安全面の配慮 ・歯磨き中は転倒に注意し、座って磨く環境を整える。歯ブラシの毛先は、子供は噛んでしまうことが多いのですぐに開いてしまいます。頻繁にチェックして新しく交換しましょう。汚れが落ちにくくなってしまいます。
大人が使う歯磨き粉の中にはフッ素濃度が高い(1450ppm)と記載してあるものもあるので6歳未満が間違って使わないように気をつけましょう。歯磨き粉やフッ素ジェルを誤ってチューブごと飲んでしまった場合(ほぼありませんが)応急手当として牛乳を飲ませ、病院を受診してください。
初期の道具選びは、使用開始時から最適な道具を選ぶことで、子どもは楽しみながら正しい磨き方を覚え、習慣化が早く進みます。
保護者は道具の使い方を伴走していく役割を担い、子どもの自立心を尊重しつつ仕上げ磨きで確認しましょう。
楽しく続けるコツと習慣づくりの工夫
初めて子どもを迎えるご家庭で、毎日の歯磨きを楽しく長く続けられるかは、親子の関係性と日常の工夫に大きく左右されます。ここでは、習慣づくりの基盤となる「親子で取り組む時間づくり」「子どもが自分でやる意欲を引き出す工夫」「ごほうびとポジティブな声かけの活用」という三つの柱を
実際的なポイントと具体例とともに解説します。生活リズムに合わせた無理のない計画を立て、みんなが楽しく取り組める形を目指しましょう。
親子で取り組む時間づくり
歯磨きを毎日の習慣として定着させるには、決まった時間と場所でのルーティン化が効果的です。
朝の忙しい時間帯には「出かける前の1分習慣」、夜は「寝る前の落ち着く時間」にセットすると、子どもも自然と受け入れやすくなります。
1) 簡単な準備をしておく。歯ブラシ、歯磨き粉、コップ、タイマーを同じ場所に並べておく。お気に入りのものが良いかもしれません。
2) 短い時間で完結する工程を作る。歯を磨く時間を約1分程度に設定し、長くなりすぎないようにする。
3) 親も一緒に行う「親子同時磨き」を取り入れる。親が手本を示すことで、子どもは安心感を持って楽しく真似しやすくなります。
子どもが自分でやる意欲を引き出す工夫
自分でやろうとする意欲を支えるには、道具選びを自分でする、自分でできた喜びを感じさせる仕掛けが有効です。実践例を挙げます。
1) 年齢に合わせた「今日は磨いたよカレンダー」を作成する。歯磨きができたら子供に好きなシールを貼ってもらう。
2) 小さな達成感の積み重ねをする。一生懸命磨いたら「前歯も奥歯もピカピカだね!」と具体的にほめて鏡を一緒に見てみる。
3) 子どものお気に入りのキャラクターやデザイン、模様などの道具で自立を促す。好きなアイテムを選ばせるとモチベーションが高まりやすい。
4) 目に見える成果を共有する。汚れがついているところを鏡で見せながら爪楊枝などで危なくないように、そっと汚れをこそぎ取り、見せる。磨いた後それが無くなったことを一緒に確認する。子どもの努力が可視化されます。
ごほうびとポジティブな声かけの活用
ごほうびは、過度にならず、行動の継続を支える軽い動機づけとして位置づけるのがコツです。物理的なごほうびよりも、気持ちがポジティブになる声かけを中心にしましょう。具体例をあげてみます。
1) 「今日も虫歯ばい菌やっつけたね!偉いね!」と努力を具体的に褒める。
2) 結果より過程を評価する。「一生懸命やったね!奥歯までちゃんと磨いてたね!」などちゃんと見ていたということが伝わるようにする。
3) ごほうびは「特別感のある体験」にとどめる。歯みがきの後に一緒に絵本を読む、交換時に親子で歯みがきグッズを一緒に選ぶ、などが嬉しいかもしれません。
4) ポジティブな声かけの頻度を増やす。歯みがき中は「あと20秒で終わるよ」磨きながら保護者が虫歯ばい菌の役をして「きゃ~!やられる~!歯ブラシがきた~!」などとすると、子どもが楽しんで一生懸命歯磨きをしてくれます。
赤ちゃんを持つお母さんお父さんに向けて、歯磨き習慣づくりのポイントをやさしくお伝えします。次は「避けるべきポイントと実践Q&A」という章で、まずはよくある失敗を整理し、次によくある質問と回答を具体的にまとめます。読み進めて役立ててください。
避けるべきポイントと実践Q&A
子どもの歯磨きを成功させるには、親の関わり方と日常の習慣づくりが鍵を握ります。
ここではよくある失敗を把握し、それぞれに対して実践的な対策を示します。短い時間でも丁寧にケアすることが重要で、焦らず一歩ずつ改善していくことを意識しましょう。
特に乳幼児期は歯茎が痒かったり使うものや口元を触られる好き嫌いの変化が大きい時期です。適切な道具選びと楽しい雰囲気作りを工夫すれば、子どもは自然と自分で磨く習慣がついていきます。
よくある失敗と対策
1) 失敗: 無理に磨かせようとして泣かせてしまう
対策: 短い時間から始める。初めのうちは例えば、一回磨くときに10秒を3回繰り返してみることを目安にして、数えながら優しく磨く。
楽しい音楽や声がけで雰囲気を和らげ、嫌がる場合は一旦中断して別の遊びを挟み、次のタイミングで再挑戦する。
2) 失敗: 親が主導で一点に集中してしまい、子どもの協力感を失う
対策: 子どもに選択肢を与える。「どの歯ブラシを使う?どの味の歯磨き粉にする?」「今日はもう少しだけやってみる?」など、簡単な選択肢を用意してやろうかなという気持ちを高める。磨く順番を一緒に決めるなど、達成感を共有する。
3) 失敗: 歯ブラシの使い方が乱暴で歯ぐきに刺激が強すぎる
対策: 子供用、仕上げ磨き用の歯ブラシを選ぶ。力を入れすぎず、子供の歯は小さいので小さく動かして優しく磨く練習をする。
このぐらい、と保護者が子供の歯にブラシを当てて力加減を伝えてあげても良いでしょう。
4) 失敗: 歯磨きタイムが日常の中で定着していない
対策: 決まった時間帯を設け、習慣化を促す。朝起きた直後と夜寝る前など、生活リズムの中に組み込む。
家族全員で同じタイミングに歯を磨くようにして、子どもにとって歯磨きが「みんなの当たり前の行動」であることを示す。
5) 失敗: 仕上げ磨きの効果を過小評価する
対策: 仕上げ磨き優しい力で丁寧にします。子供さんは必ず磨き残しをします。丁寧にケアすることを重視し、毎日子供が自分で磨くあとに仕上げ磨きをセットで入れる。
特に残りやすいのは、下の奥歯の内側と上の奥歯の頬っぺた側です。
よく見ることができていると口腔内の状態を確認し、変化に気づけるようになります。
よくある質問と回答
Q1: 何歳くらいから仕上げ磨きを始めれば良いですか?
A1: 歯が生え始めたら、もう始めましょう。親子で楽しく習慣化することが大切です。
Q2: 子どもが嫌がるときのベストな対応は?
A2: 嫌がる原因を探り、短時間・低負荷から始める。
歯磨きを「楽しい遊び」と結びつけ、褒め言葉や小さなご褒美を活用します。無理に続けず、タイミングを見てお口の中をのぞく、触るなど有効かと思います。
Q3: 歯磨き粉の量はどう決めればいいですか?
A3: 乳児~幼児期は「米粒大程度」または子供が「おいしくない」と感じない程度のごく少量を目安にします。
前述にも書きましたが、フッ素濃度は年齢によって使える濃度が変わりますので、歯医者さんでフッ素濃度がちゃんと書いてあるもの、どの濃度を使えばよいかを尋ねましょう。
Q4: ついつい寝落ちしてしまいます。どうすれば続けられますか?
A4: 寝る前のルーティンを見直し、歯磨きを日課の最後の工程として固定します。食べ終わったら歯磨きに誘導するなどを習慣化できればよいでしょう。
Q5: 上手に仕上げ磨きができるよう、家庭でのフォローアップは何をすべきですか?
A5: 歯が生え始めたら、もう歯科医院に行き慣れさせると良いです。定期健診は必ず行くようにしましょう。
間隔は3~6か月を目安に定期健診をたいていします。その時に歯科でのフッ素も塗りますし、磨き方のアドバイスも歯科医師や歯科衛生士から受けられます。
この章では「避けるべきポイント」と「実践的なQ&A」を組み合わせ、日常の中で即使える対策を中心にまとめました。
章全体の流れを通じて、失敗を恐れずに徐々に習慣化していく姿勢を大切にしてください。
お子さんの歯磨きや歯並びの心配、そのほかの質問にお答えするオンラインセミナーもしております。児童館や子供の施設などでも可能です。ご希望の場合は、お問い合わせください。